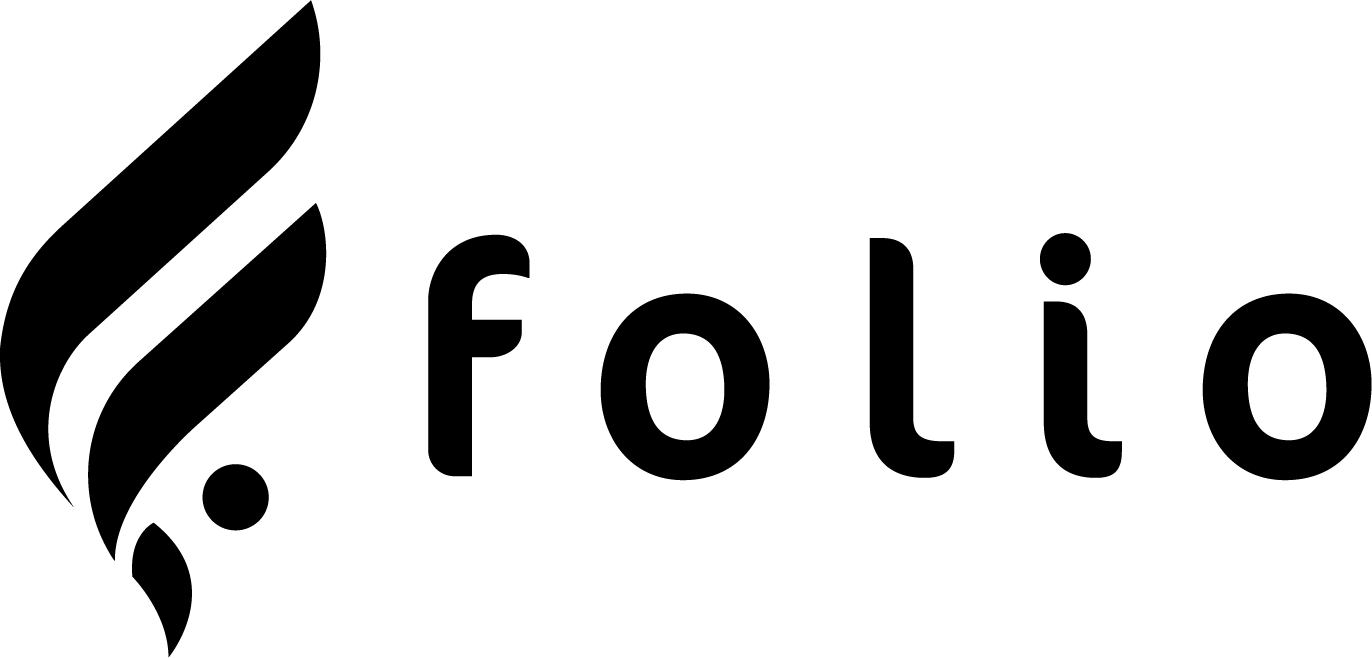「ニーズ」は“欲しい”ではなく、“困っている”から生まれる。
「ニーズを掴め」という言葉は営業の現場でよく耳にします。 しかし、多くの営業が誤解しているのは、ニーズ=欲しいものだと思い込んでいることです。本質的にはそうではありません。
ニーズとは、「現状と理想の間にある“問題”や“不満”」のことです。たとえば、
- 人手が足りない
- 集客が安定しない
- 社員が定着しない
これらは“問題”や“不満”という形で現れます。そして、その不満が放置できないほど大きくなったとき、初めて「欲求」に変わる。つまり、ニーズとは「不満」から芽生え、「欲求」へと育つものなのです。満足している相手に、何を提案しても刺さりません。満足度100%の状態から、わずか1%でも「不安」「不便」「不満」が生まれた瞬間——そこに商機が生まれます。その小さな“ひずみ”を丁寧に言語化していくのが、営業の仕事です。
商談が成立するのは「方程式」で決まっている。
「センスのある営業が売れる」と思われがちですが、実は商談には明確な“方程式”があります。 この“方程式”を理解し、再現可能に扱うことが重要です。
商談成立の方程式
問題の重要度(深刻さ) > 解決にかかるコスト
どれほど優れたサービスでも、顧客が「今のままでも困っていない」と感じている限り、契約には至りません。逆に言えば、「問題の重大さ」を相手自身に実感させることこそ、営業の腕の見せどころです。
たとえば「採用が難しい」という表面的な悩みの裏には、「現場の負担が増え、若手が辞め、事業拡大が止まる」という連鎖的な損失があります。それを質問によって顧客自身に気づかせることで、“解決コスト”がむしろ“小さく見える”状態をつくる。そしてこのとき初めて、顧客の口から「このままでは事業が止まる」「今のうちに採用を整えないと」など、自ら行動を正当化する“導入理由”が語られ始めます。営業の役割は、説得ではなく、相手の中にある小さな“不満”を、重大な“痛み”として自覚させる質問をすることです。